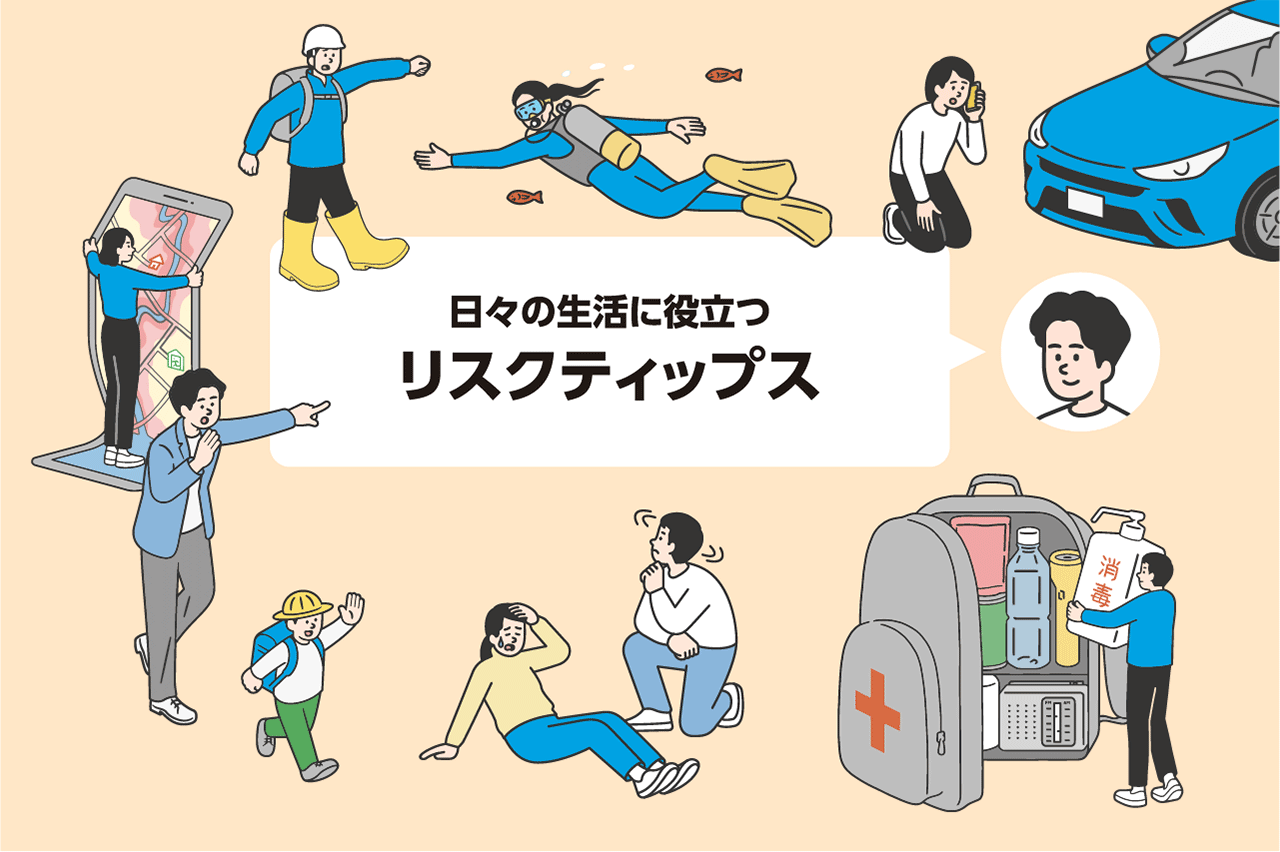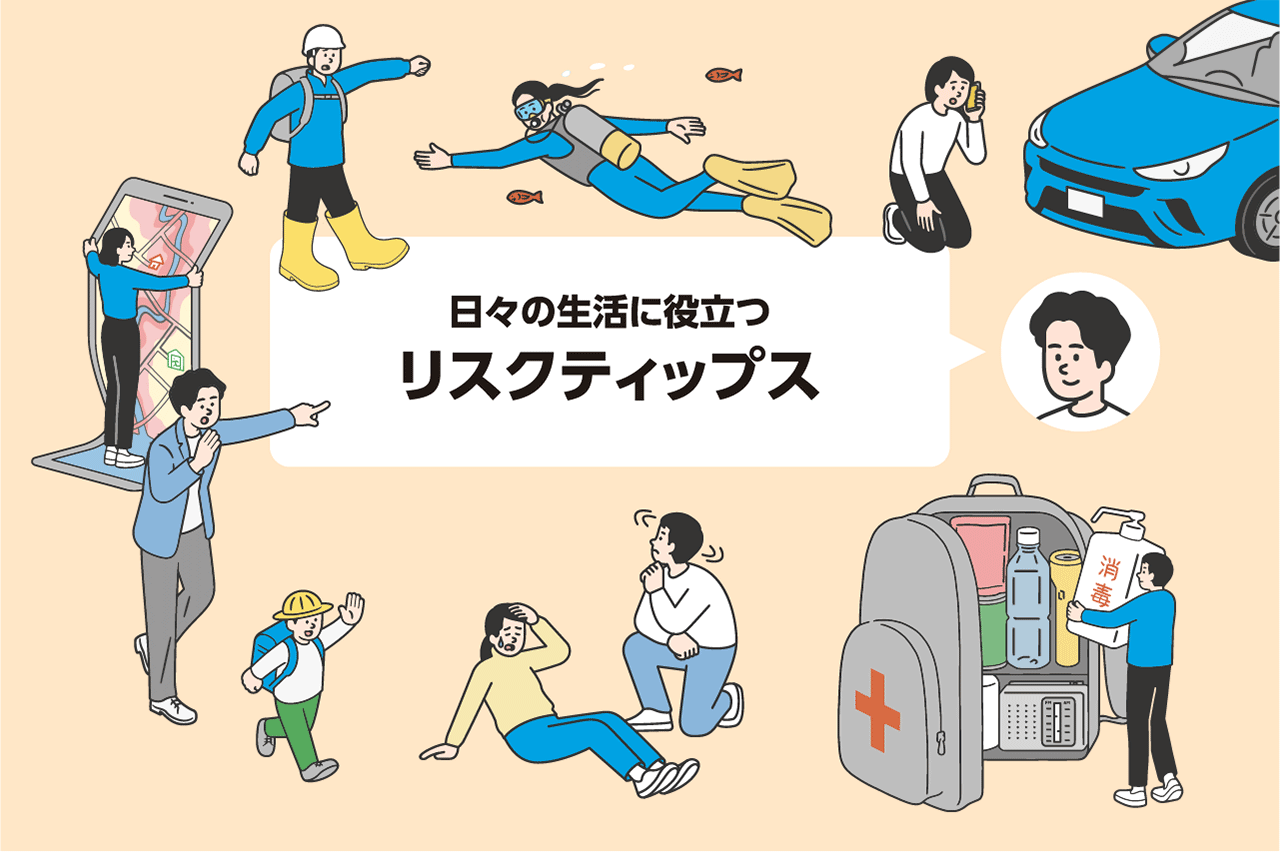たびたび発生する台風や集中豪雨で、河川の氾濫や土砂災害、道路の冠水など、生活や生命がおびやかされる自然災害のリスクは年々高まっている。「自分たちが暮らす地域は大丈夫なのか?」そう思ったとき、住所や郵便番号を入力するだけで水害リスク*1だけでなく地震・津波のリスクを「マイホームリスクマップ*2(https://sb-appvantage-pro3.hclvoltmx.net/apps/AIGRiskMap/)」で事前に把握することができる。
制作にあたった個人火災保険部 企画推進課の森野 恵菜に、「マイホームリスクマップ」の使い方、制作背景や込められた思いについて聞いた。
*1 本記事では、「水害リスク」は洪水、高潮、内水氾濫など、水が原因で発生する様々な災害リスクを包括的に表す用語として、「水災リスク」は水害リスクのうち、洪水や高潮などの火災保険で補償される水害に関するリスクを表す用語として使用。
*2 旧「水災等地確認マップ」。リスク対策にお役立ていただけるサイトであることが分かるサイト名称に変更。
地域間の水災リスクの違いを知り、契約見直しの機会に
2024年10月1日より、火災保険の改定が実施され、全国一律だった水災補償の保険料率は、河川の氾濫や土砂災害などの水災リスクに応じた5段階に細分化されている。具体的には、市区町村ごとに水災リスクがもっとも低い地域の「1等地」から、もっとも高い地域の「5等地」までに分かれている。これにより、地域間の水災リスクの違いが、保険料にも反映されることになった。
「保険料が高くなってしまうから、水災の補償は付けないでおこう」や「1等地でリスクが低いから水災の補償は不要だろう」と考えられるお客さまもいるかもしれない。ただ、住んでいる地域によってリスクはさまざまである。
「海や河川から離れているから……」「マンション住まいだから……」といった理由で水災補償を付けずに火災保険を契約している方々のなかにも、今回の水災リスクの細分化を機にあらためて契約内容を見直したほうがよい場合がある。最近の集中豪雨では、マンホールや側溝から雨水が地上にあふれるといった、都市型の洪水による被害が発生している。
「災害にあってから水災補償も付けておけば良かったと後悔されることがないよう、ぜひマイホームリスクマップでお住いの地域の水災等地や災害リスクを確認してみてください。事前にリスクを把握し、納得して火災保険にご加入いただくことが重要だと考えています」(森野)
「水災等地」タブ イメージ図
身の回りの災害リスクと避難場所が同時に確認できるマップ
「マイホームリスクマップは、シンプルで難しい操作なく多くの人が簡単に使えることをいちばんに考えて作りました。住所または郵便番号を入力するだけで、「水災等地」「水害リスク」「地震・津波リスク」のタブが表示され、それぞれの災害リスクが確認できます」(森野)
ハザードマップで一度は身のまわりの災害リスクを調べたことがあるという人は多いかもしれない。AIG損保が提供するマイホームリスクマップでは、地図上で水害や地震・津波のリスクがどのくらいなのか、ハザードマップ上で確認しながら、その地域がほかの市区町村に比べて相対的にどのくらい水災リスクが低いか高いか、「等地」によって確認することができる。
「水災等地とハザードマップ情報の両方を同じ画面で確認しながら、ご自身の火災保険に水災補償をつけるかどうかを判断することが大事だと思います。また、意外と見落としがちなのが、水害と地震や津波では避難場所が違う場合があるということ。
『水害リスク』と『地震・津波リスク』のタブに表示されている避難マークをクリックすると『避難場所の住所』だけでなく、洪水、崖崩れ、地震、津波など『対応している災害の種別』も表示されるようになっています。マイホームリスクマップが、家族で避難場所を確認するきっかけにもなるとうれしいです」(森野)
2025年8月からは、「水害リスク」と「地震・津波リスク」のタブで「保険補償事例」を掲載している。事例は水災、土砂災害、地震に関するもので、水災、地震の事例では「戸建て」と「マンション」それぞれの損害を確認することができる。これらの事例は、どのような被害や損害が発生するのか、具体的にイメージすることに役立つと考えられる。
「水害リスク」タブ イメージ図
「地震・津波リスク」タブ イメージ図
万一の場合には「印刷」ボタンの活用を
マイホームリスクマップの便利な点は、これだけではありません。二次元コードを読み取ればすぐにスマートフォンやタブレットで表示できるだけでなく、「印刷」ボタンもわかりやすく表示されている。
「ペーパーレスがあたり前の時代に、印刷する必要があるのかという意見もありました。ですが、いざ避難が必要な状況になったときのネット環境や、その時に落ち着いて検索できる状況かどうかは誰にもわかりません。
マイホームリスクマップでは、こういった災害時の情報途絶リスクに備えていただくために、パソコン版では「印刷」機能を実装しています。代理店がお客さまに契約案内を郵送する際に印刷したマップを同封するケースや、お客さまご自身がご家族と避難場所を共有するために印刷したマップをいつも見えるところに貼っておくなどのニーズがあると考えました」(森野)
個人火災保険部 企画推進課
森野 恵菜
大事なのはリスクマネジメント
今後、「水害や地震・津波以外のリスクに関する情報も提供していきたい」と森野は意気込む。たとえば最近では、道路のアンダーパスのリスクが大きくなってきた。
アンダーパスとは、交差する鉄道や道路などの下を通過するため、周辺の地面よりも低くなっている道路のこと。ここは地形的に雨水が集中しやすい構造となっているため、集中豪雨によって冠水し車両が水没するなどの重大な事故が発生しやすい場所でもある。
「避難場所に向かう道中に、高リスクのアンダーパスがあると事前にわかっていればリスクを回避できます。旅行先など慣れない場所での災害リスクを回避するためにも、こういった情報が役立ちます。ご自身やご家族の災害リスクはご自身でマネジメントすることが大切なので、マイホームリスクマップがその一助になることを願っています。
現状では、できる限りシンプルに機能を削ぎ落としているマイホームリスクマップですが、今後は事前にリスク回避につながる情報をもっと提供していきたい。多くの方々にマイホームリスクマップを活用していただき、どのような情報が必要か、どういったツールにすると使い勝手がいいか、たくさんの声をいただけるとうれしいですね」(森野)
2025年8月に掲載を開始した「保険補償事例」も代理店の声からだ。他にも、お客さまがより正しくリスクを知り、適切な備えにご活用いただくことを目的に、一般財団法人 日本気象協会が運営するサイト「知る防災」へのリンク機能を搭載するなど、バージョンアップを実施した。多くの方の役に立つサイトになるために、さらなるバージョンアップに取り組んでいく。