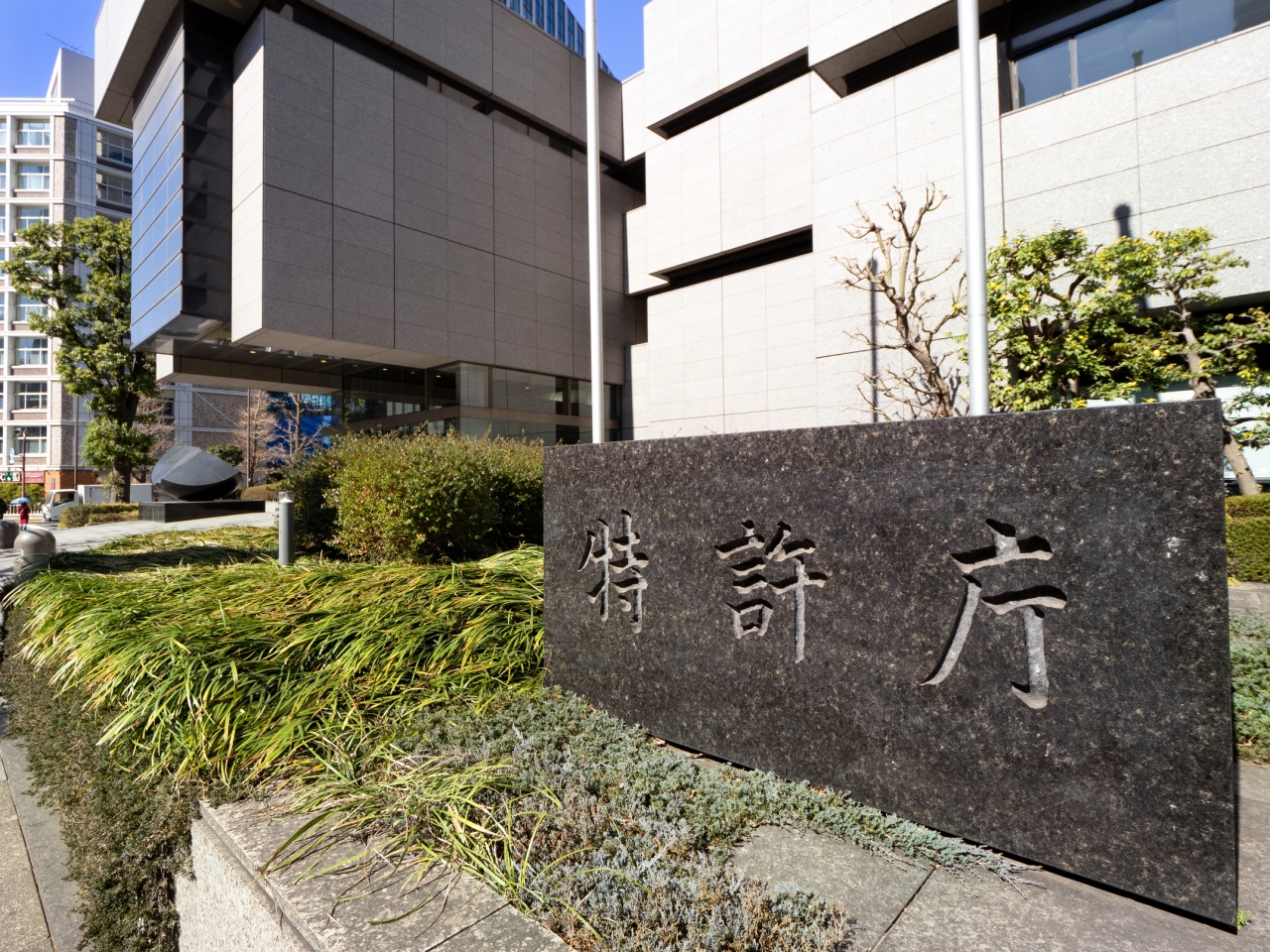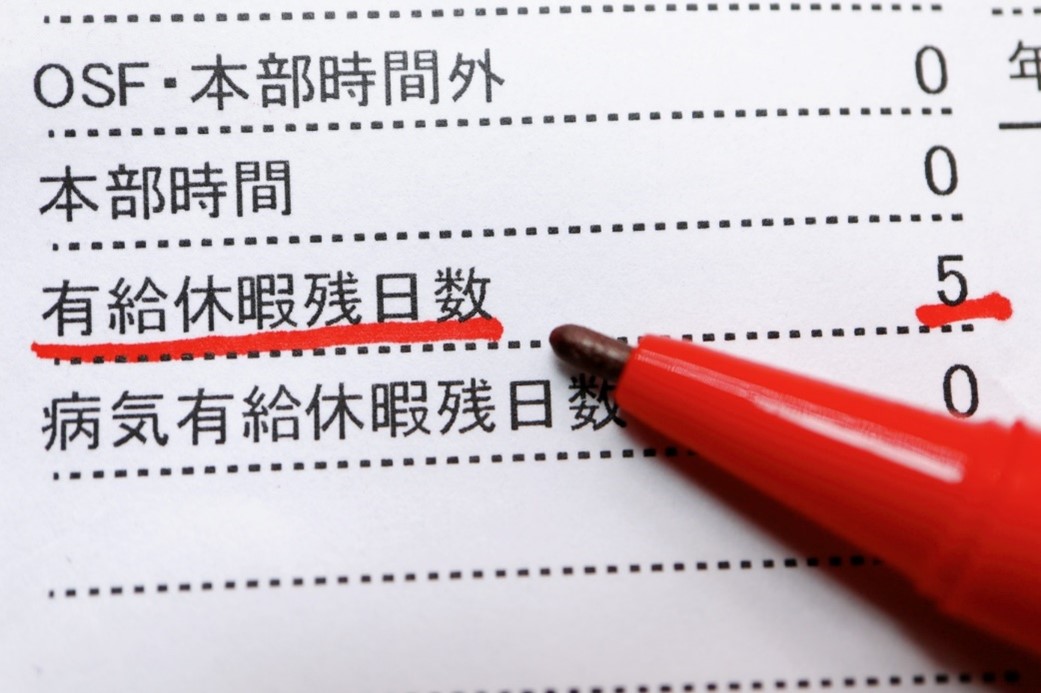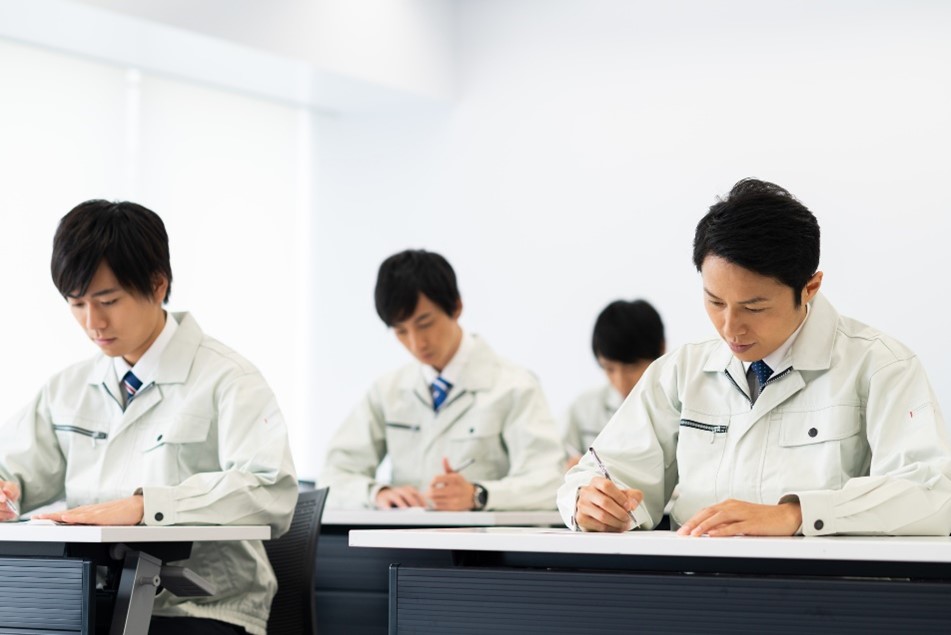-
地震災害とは地震によって引き起こされる自然災害のこと -
発生リスクの高い大規模地震 -
地震災害の種類 -
地震災害に備えて企業ができる対策 -
地震災害への理解を深め、継続的な災害対策を実施しよう
地震によって引き起こされる地震災害は、人命や社会インフラに加えて、企業の事業継続に対しても多大な影響を及ぼす可能性があります。地震による被害を最小限に抑えるには、事前の準備が欠かせません。
ここでは、地震災害の種類や、企業ができる備えについて解説します。
地震災害とは地震によって引き起こされる自然災害のこと
地震災害とは、地震が原因となって起きるさまざまな自然災害を指します。
地震は、地下の岩盤が周囲から押されたり、引っ張られたりしてずれることで膨大なエネルギーが発生し、地表に強い揺れを生じさせる自然現象です。地震の規模はマグニチュードで表され、ある場所における地震の揺れの強弱の程度は震度で表されます。2011年に起きた東日本大震災(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震)は、マグニチュード9、最大震度は7(宮城県栗原市)でした。
一般的に震度5強以上になると、固定していない家具が倒れたり、耐震性の低い建物を損壊したりといった被害が見られるようになるほか、地震火災や液状化現象、津波などが発生する可能性が高まります。
企業が受ける地震災害による被害は、建物・設備・商品などの物理的な破損、企業運営や供給チェーンの中断、情報システムの損害、従業員への被害などが挙げられます。このほか、地震災害では災害関連死(災害による負傷の悪化や避難所生活が原因で体調を崩し死亡したと認定されたもの)があり、2016年に発生した熊本地震では220人が犠牲となりました。
企業は、地震と地震災害の危険性を正しく把握し、必要な備えをしておくことが大切です。
出典:「東日本大震災 ~東北地方太平洋沖地震~ 関連ポータルサイト」(気象庁)
発生リスクの高い大規模地震
日本は地震多発地域であり、今後も複数の大規模地震が発生することが予測されています。中でも発生リスクが高く、甚大な被害が懸念されているのが、南海トラフ地震と首都直下地震です。
■日本での発生が想定されている大規模地震
画像引用:内閣府防災情報ページ「地震災害」
南海トラフ地震
南海トラフ地震は、西日本全域におよぶ超広域震災として警戒されている地震です。
南海トラフは、静岡県の駿河湾から九州の日向灘にかけての海底にある、水深4,000m級の深い溝状の区域のことで、過去に大きな地震が繰り返し発生しています。南海トラフ地震が発生した場合、震度6~7の強い揺れが広範囲にわたり、10メートルを超える津波をもたらすとされています。特に津波は沿岸地域に甚大な被害を与える可能性が高く、十分な備えが必要です。
南海トラフで30年以内にマグニチュード8~9クラスの地震が発生する確率は、2020年1月24日時点で70~80%と予測されています。また、2024年8月8日19時15分に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が初めて発表されました。
南海トラフ地震臨時情報とは、南海トラフ沿いで異常な現象が観測されたり、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価されたりした場合に、気象庁から発表される情報のことです。今後も同様の発表が行われる可能性があるため、注意しておきましょう。
南海トラフ地震による死者数は、揺れによる被害が最大となると想定される「陸側ケース」および「東海地方が大きく被災するケース」で23万1,000人、経済的被害額は171兆6,000億円と試算されています。
出典:「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)について」「南海トラフ地震について」(気象庁)「南海トラフ地震臨時情報が発表されたら!」(内閣府)
首都直下地震
首都直下地震とは、東京を中心とする首都圏で発生すると想定されるマグニチュード7クラスの地震のことです。震源地は東京都だけでなく、茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県、または山梨県を含む南関東地域のどこかである可能性があります。30年以内にマグニチュード7クラスの首都直下地震が発生する確率は、予測として2020年1月24日時点で70%程度です。
首都直下地震による死者は、最悪のシナリオではおよそ2万3,000人に達し、その7割にあたる1万6,000人が火災により死亡するとされています。また、経済的被害額はおよそ95兆円に達する見込みです。
出典:「特集 首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)‐内閣府防災情報のページ」(内閣府)
地震災害の種類
地震は、揺れによる直接の被害だけをもたらすわけではありません。地震によって引き起こされる主な災害には、次に挙げるような強い揺れによる建物などの損壊のほか、地震火災や液状化現象、津波などもあります。
強い揺れによる建物などの損壊
地震の揺れそのものが引き起こす直接的な被害には、建物の倒壊や損壊、道路、橋などのインフラの破損が挙げられます。強い揺れにより家屋やオフィスビルが倒壊し、多くの人命が失われることも少なくありません。
強い揺れによって主要な交通網が破壊されると移動が困難になり、物資の供給が絶たれます。送電線の破損や発電所の運転停止、水道管やガス管の破裂などが起きると、電気・水道・ガスの供給が停止し、生命維持や産業活動にも大きな影響が生じるでしょう。
地震火災
地震火災は、地震による揺れが原因で発生する火災のことです。地震の揺れによって、使用中のコンロなどの火に直接可燃物が落ちる、ガス管が破裂してガス漏れが発生する、電気配線の破損によりショートが起きるなどさまざまな原因で火災が発生します。
地震火災は、複数の場所でガス管が破裂したり、各家庭でガスコンロを使用していたりすることが原因で同時多発的に発生する確率が高い火災です。その上、地震の影響で交通インフラが混乱し、消火活動が途絶えて消火に時間がかかるほか、風などに煽られて急速に広がることが多く、大規模な被害を引き起こします。特に都市部は建物が密集しているため、火災のほか火災旋風(火災を含んだ竜巻状の渦)にも注意が必要です。
液状化現象
液状化現象は、地震の揺れによって地盤が液体のような状態に変化し、支える力を失う現象です。液状化現象が起きると、建物や道路が傾いたり沈み込んだりする甚大な被害が発生します。
液状化現象は特に埋立地など地盤のゆるい地域で発生しやすく、その影響は広範囲に及ぶことがあります。
津波
津波は、海底の地震やそれに伴う地形の変動によって引き起こされる巨大な波です。津波は非常に高速で移動し、短時間で海岸に到達、高さによっては上陸します。
津波の破壊力は非常に強力で、巨大な水圧を保ったまま押し寄せる押し波と、反対に沖へ海水を引きずり込む引き波によって沿岸部の建物やインフラ、人命に甚大な被害をもたらします。また、2011年の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の事故に見られるように、沿岸部に位置する発電所への影響も大きな懸念事項です。
地震災害に備えて企業ができる対策
企業が地震災害発生時の被害を最小限に抑えるには、地震によって自社が受ける被害を想定した上での備えをしておくことが重要です。以下、地震災害に備えた事前対策について解説します。
■地震災害に備えて企業ができる主な対策
従業員の安全対策
地震災害への備えとして、従業員の安全対策を実施します。具体的には、安否確認を行うための連絡方法の確立や、オフィスからの避難場所と経路の確認、非常用品の備蓄などです。
安否確認は、緊急時に情報共有ができるシステムの構築を行い、従業員が使えるようにしておきます。備蓄については、救急キット、懐中電灯、簡易トイレ、ブランケットなどの非常用品を準備し保管します。非常食や水は、最低でも3日分以上を用意しましょう。
防災グッズについては、こちらの記事をご覧ください。
地震で避難する際の持ち物とは?会社に備えたい防災グッズリスト
従業員の安否確認については、こちらの記事をご覧ください。
オフィス什器の転倒や落下対策
地震災害が起きる前に、オフィス什器の転倒や落下対策を実施します。オフィス内の書棚やファイルキャビネットなどのオフィス家具は壁に固定し、PC、モニター、プリンター、コピー機などの重い機器は高い場所に載せないといった対策が必要です。
キャスター付きの機器などは、着脱式の移動防止ベルトや下皿の設置などで移動を防ぎましょう。書棚やファイルキャビネットの扉にはロック機能を付け、中の物が飛び出さないようにすることも忘れずに行ってください。
出典:「オフィス家具類の転倒・落下・移動防止対策」(東京消防庁)
建物の損壊、窓ガラスの落下対策
オフィス什器の転倒防止といった建物内の対策と併せて、建物自体の対策も施しましょう。
建物が自社ビルであれば耐震工事を行い、賃貸であれば新耐震基準に適合している物件を選ぶことが推奨されます。また、建物の損壊が起きた場合を想定し、避難経路に障害物となる物を置かない、緊急照明を設置するなどの対策が必要です。窓ガラスに飛散防止フィルムを施工することでも、地震時の安全性を高められます。
リスクアセスメントの実施
地震災害が事業に及ぼす影響を評価し、対策を講じるためにリスクアセスメントを実施することも重要です。
リスクアセスメントは、職場におけるリスクを定量的に見積もり、対策の優先度を決めて、危険な要因を除去・低減する活動です。施設の物理的な耐性評価と補強、代替を含む供給チェーンの確保など、地震による被害を予測し、それに対応する計画を立てましょう。
事業継続力強化計画(BCP2.0)の策定
地震災害に備えて、事業継続力強化計画(BCP2.0)を策定しましょう。事業継続力強化計画(BCP2.0)とは、企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の事前準備を行うために必要な項目を盛り込んだ計画です。事業継続力強化計画(BCP2.0)は従来の事業継続計画(BCP1.0)とは異なり、計画づくりよりも事業継続力の獲得と継続的な改善が重視されます。
事業継続力強化計画(BCP2.0)を策定しておくことで、地震災害後の事業運営を再開しやすくなります。
事業継続力強化計画(BCP2.0)などについては、こちらの記事をご覧ください。
地域社会との連携強化
企業は地震災害に備えて、地域全体で支え合う連携を強化しておきましょう。災害が起きた場合、地域内のほかの企業や組織との連携が不可欠です。災害用に備えた備蓄や機材などを、自社だけではなく地域全体でも使えるように準備します。その上で、備蓄共有や情報交換といった、相互支援を可能にする企業同士のネットワークを確立することで、地震災害が起きた場合に、地域全体での復興を早めることにつながります。
火災対策
火災対策も、地震災害に備える上で重要です。例えば、地震に伴う火災に備えるために非常時用の消火器を各階ごとに配置し、その使用方法を全従業員が理解していることを確認します。併せて定期的な消火訓練の実施も重要です。
消火器の設置が義務づけられている建物は消防法によって細かく定められているため、自社に正しく消火器が設置されているか確認しておきましょう。
津波対策
沿岸部にオフィスや施設を構える企業は、地震災害への備えとして津波対策を怠ってはいけません。
避難経路や避難所の位置の従業員全員への周知と、津波が発生した場合に備えた定期的な避難訓練の実施を欠かさず行いましょう。実際に津波が押し寄せたときに迅速かつ安全に避難するための、周到なシミュレーションをしておくことが重要です。
地震災害への理解を深め、継続的な災害対策を実施しよう
南海トラフ地震や首都直下地震は、今後いつ発生してもおかしくない状況となっています。大規模な地震災害は、企業にとって大きな試練となりますが、事前の備えがあればその影響を極力抑えることができます。事業継続力強化計画(BCP2.0)の策定や従業員の安全確保など、必要な準備を怠らないことが非常に重要です。
地震災害に備えるための継続的な取り組みが、企業の安全と成長を支えるキーポイントとなります。地震災害について理解を深め、事業継続のために企業ができる対策を確認して、継続的に災害に備えることが大切です。
MKT-2024-518
「ここから変える。」メールマガジン
経営にまつわる課題、先駆者の事例などを定期的に配信しております。
ぜひ、お気軽にご登録ください。
関連記事
パンフレットのご請求はこちら
保険商品についてのご相談はこちらから。
地域別に最寄りの担当をご紹介いたします。
- おすすめ記事
- 新着記事