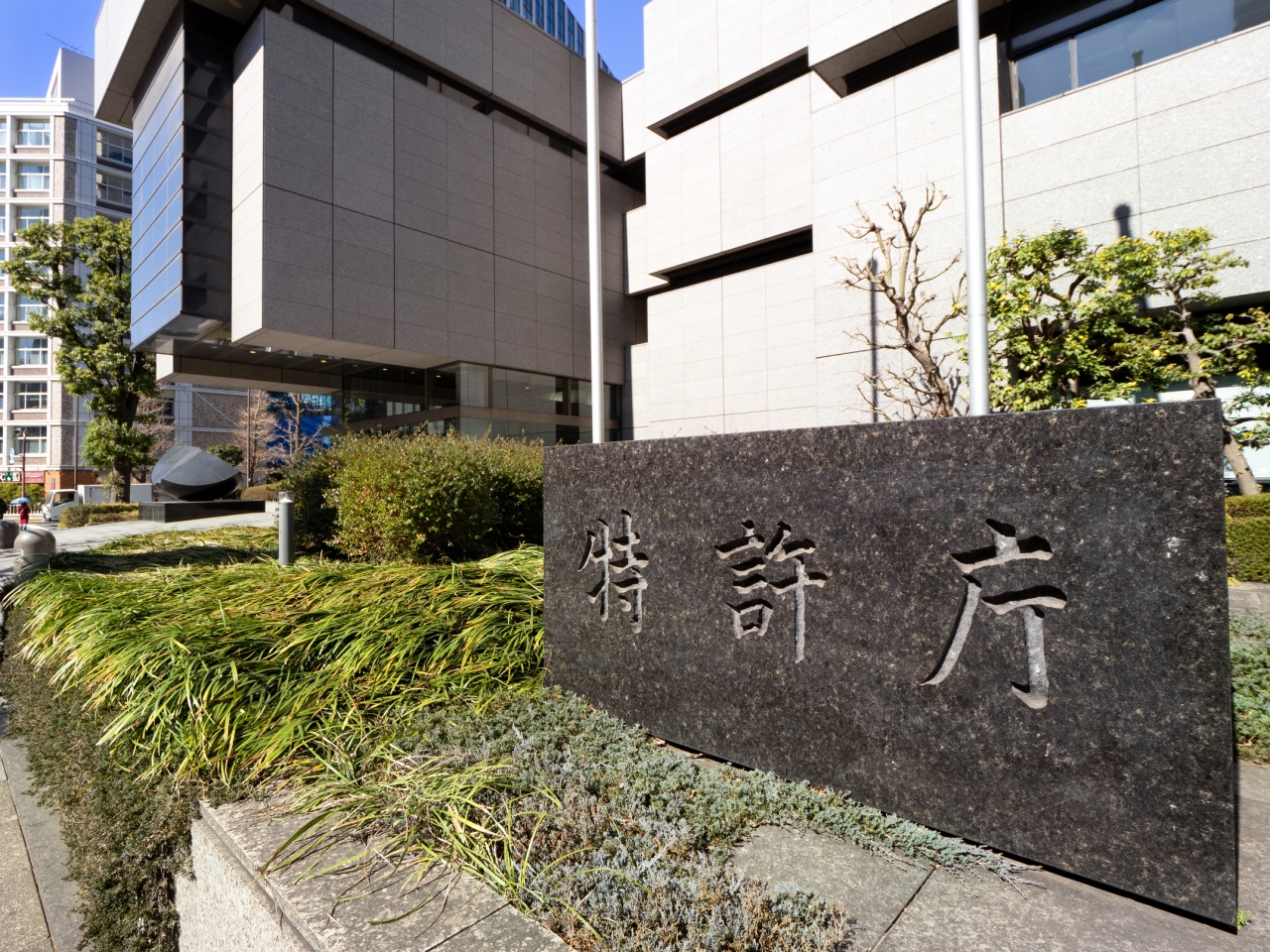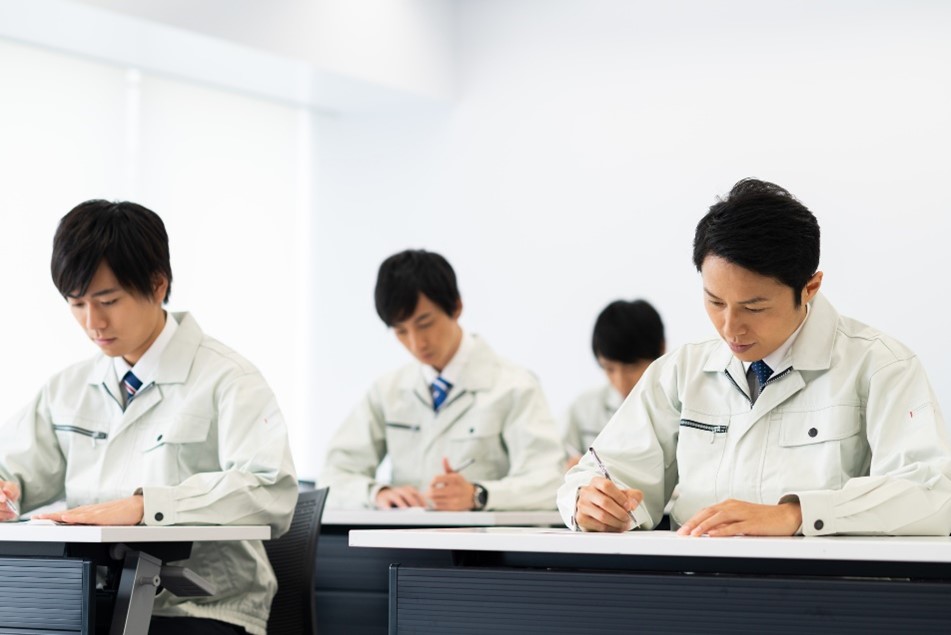-
火山災害とは火山の活動によって引き起こされる自然災害のこと -
日本は世界有数の火山国 -
火山災害の要因 -
火山災害に備えて企業ができる対策 -
火山災害に備えて企業の防災戦略を万全にしよう
火山災害は、噴火をはじめとする火山活動によって、施設の破壊や物流の停止、火山灰による被害など、企業にとって無視できない自然災害です。火山災害を引き起こす要因には噴石、火山灰、火山泥流などがあり、人命や財産、事業活動に深刻な影響を及ぼす危険性があります。
ここでは、火山災害を引き起こす要因や、企業ができる備えについて解説します。
火山災害とは火山の活動によって引き起こされる自然災害のこと
火山災害とは、噴火をはじめとする火山活動によって引き起こされる自然災害のことです。火山活動は地球内部の熱エネルギーが高温物質の移動を通じて外部に放出される現象であり、特定の条件下で活発化します。
火山活動には噴火や火砕流、火山ガスなどがありますが、中でも噴火は最も激しい火山活動のひとつです。噴火が起きると火山の下に溜まった高温のマグマやガス、岩石が地表に放出され、しばしば周囲の環境や人々の生活に対し、火山災害として深刻な影響を及ぼします。
日本は世界有数の火山国
日本は世界有数の火山国で、活火山が111座あり、世界の活火山の約1割を占めています。活火山とは過去1万年以内に噴火した火山や、現在も活発な活動のある火山のことです。
■世界の活火山の分布図
画像引用:「わが国の火山災害対策」(内閣府)
日本では、気象庁が火山活動に対する監視体制を整備しています。火山災害の軽減のため、全国111座の活火山を対象として観測・監視・評価を行っており、その結果にもとづいて警戒すべき変化が起きたときは噴火警報や予報を発表しています。
出典:「わが国の火山災害対策」(内閣府)、「各火山の活動状況」(気象庁)
火山災害の要因
火山活動によって引き起こされる災害にはさまざまな要因があります。噴火によって火山から噴出される噴石や火山灰、火山ガスといった、火山噴出物から受ける直接的な被害のほか、噴火に伴って発生する火山泥流や山の崩壊などによる被害も火山災害です。
ここでは、主な火山災害の要因について解説します。
出典:「火山噴出物に関する用語」「主な火山災害」(気象庁)
噴石
噴石は、火山の噴火によって火口付近から吹き飛ばされる石のうち、防災上警戒が必要で、注意すべき大きさの岩石を指します。
気象庁では防災上、大きな噴石は概ね20~30cm以上、小さな噴石は数cmと定義していますが、いずれも直撃すれば生命に危険が及ぶ可能性があります。
火山灰
火山灰は、噴火によって排出される固形物の中で、直径2mm未満の粒子が細かい物を指します。
主に尖ったガラス質でできているため、目に入ると角膜を傷つけたり、肺に入ると炎症を起こしたりするなど、健康問題を引き起こすことがあります。このほか、火山灰は風に乗って広範囲に降下するため、農作物に甚大な被害を与えます。火山灰が車や飛行機に吸い込まれると故障につながり、重大な事故を引き起こしかねません。
火山泥流・土石流
火山泥流は、噴火による湖の決壊や急激な融雪などによって発生する泥水が、岩石や木を巻き込みながら流下する現象です。また、火山灰が降り積もった地域に大雨が降り、火山灰と水が混ざり合って流れ出す泥流を指すこともあります。このほか、水と土砂が混ざり合い、低地へ一気に流れ出る土石流にも注意が必要です。
これらの泥流は非常に高速で流れ、規模が大きいと橋梁の破壊や家屋の埋没を引き起こすため、大変危険です。また、生態系に深刻な影響をもたらすこともあります。
火砕流
火砕流は、高温のガスと大量の火山噴出物が混ざり合って山腹を流れ落ちてくる現象です。
非常に高温、そして時速100km以上という高速で移動するため、火砕流を目視してから逃げようとしても逃げ切ることは困難です。
地形的に低いところを流れ落ち、その風圧は樹木をなぎ倒すほど強力で、含まれる高温の物質は建物や車両を焼き尽くすこともあります。
溶岩流
溶岩流は、火山の火口や地殻の割れ目から噴出したマグマが地表を流れ出る現象です。
マグマが冷却・固化してできた岩体も溶岩流と呼ばれます。流れる速度は人の歩く速度と同程度かそれ以下ですが、流れをせき止めることはほぼ不可能です。
建物やインフラなど接触するものに大きな被害を与え、ときには地形を変えるほどの影響を与えることもあります。
火山ガス
火山ガスは、火山の火口や噴気孔から放出される気体成分の総称です。水蒸気、フッ化水素、塩化水素、二酸化硫黄、硫化水素、二酸化炭素、メタンなどさまざまな成分が含まれます。
これらのガスは、地下のマグマに溶けていた揮発性成分が圧力低下などによって発泡し、地表に放出される気体です。高濃度になると健康への危険度が増します。各種のガスが呼吸困難や目への刺激を引き起こし、長時間続くと深刻な健康問題をもたらすこともあります。
火山災害に備えて企業ができる対策
ここでは、土砂災害に備えて企業ができることを解説します。
土砂災害は山や崖など、広範囲に対策が必要で、多くは国や自治体による大規模工事を必要とします。事業所が土砂災害のおそれのある地域に所在する場合、企業としては自治体への働きかけのほか、従業員の安全を確保することが大切です。
■火山災害に備えて企業ができる主な対策
活火山分布の確認
まず、火山災害に備えて、事業所の近くにある活火山について確認します。
火山が噴火した場合、噴石や火砕流、火山灰などの災害は、火山の種類や位置によって異なり、どの災害にあうかはわからないため、それぞれに応じた備えが必要です。
活火山の分布については、産総研知識調査総合センターや気象庁の情報が役立ちます。産総研知識調査総合センターの活火山分布図は、各火山の過去1万年間の噴火履歴を確認できます。気象庁の各火山の活動状況では、気象庁が発表している火山情報などを確認することが可能です。
活火山分布についてはこちらをご参照ください
「活火山分布図」(産総研知識調査総合センター)
「各火山の活動状況」(気象庁)
噴火警戒レベルと取るべき行動の確認
噴火警戒レベルは、気象庁が火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や地域住民などが「とるべき防災対応」を5段階に区分して発表する指標です。この内容を事前に把握し、企業としてできる適切な対応を準備しておきましょう。
レベル1~5の噴火警戒レベルの内容は下記のとおりです。特にレベル5は、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、または切迫している状態にあることを示します。すみやかな避難が必要な状況なので、冷静かつ迅速な行動が求められます。
噴火警戒レベルと取るべき行動の確認についてはこちらをご参照ください
「噴火警戒レベルの説明」(気象庁)
■噴火警戒レベル
画像引用:「噴火警戒レベルの説明」(気象庁)
従業員の安全対策
火山災害が発生した際の従業員の安全対策を施すことも、企業ができる大切な対策のひとつです。具体的には、連絡網や安否確認方法の確立や、避難場所と経路の確認、非常用品の備えなどです。
連絡方法は、電話やスマートフォンに加えて、一斉配信や自動再配信、データ自動集計などができる安否確認システムの導入も役立ちます。避難場所と避難経路についても周知し、作成した避難計画に沿って定期的に避難訓練を行うことも重要です。
火山災害を想定した備えとしては次の物が推奨されます。
<火山災害に対する備蓄品の例>
・備蓄:非常食、水
・衛生品:救急キット、懐中電灯、簡易トイレ、ブランケット
・火山災害対策:防塵マスク、ゴーグル、ヘルメット、防水シート、雨具
また、事業所が火山現象の影響範囲内にあった場合、従業員が業務中に被災する可能性があります。必要に応じて負傷者に対する医療支援を手配できるように準備しておくことや、就業できなくなった従業員の代替要員をどのように確保するのか、検討しておくことも大切です。
従業員の安否確認については、こちらの記事をご覧ください。
リスクアセスメントの実施
火山災害に備えて、リスクアセスメントを実施します。
リスクアセスメントは、職場や事業場に存在する危険性や有害性を調査して特定し、それらのリスクを見積もり、優先度を設定してリスク低減措置を決定する手順です。
また、火山活動が活発化する可能性のある地域に事業所が存在する場合は、火山災害が事業に及ぼす影響を評価し、対策を講じる必要があります。
例えば、火山灰の重量による屋根の損傷程度を物理的な耐性評価で見積もり、それに応じた構造物の安定性を確保するための補強をするといった対策です。そのほか、従業員の危険性に関わるシミュレーションと安全確保対策の構築や、サプライチェーンに対するリスク調査と供給確保のための仕組み作りなどを行います。
事業継続力強化計画(BCP2.0)の策定
事業継続力強化計画(BCP2.0)は、自社の災害リスクに関する認識にもとづいて、企業の防災・減災対策を詳細に取り決める計画です。従来の事業継続計画(BCP1.0)とは異なり、計画の作成のみにとどまらず、実効性ある事業継続力の獲得と継続的な改善が重視されます。企業が火山災害に備えて策定しておくべき、重要な計画といえるでしょう。
例えば、物流や輸送に関係する事業の場合、火山灰によって交通機関が不通になることが想定されます。活火山分布図などを確認し、別ルートや別エリアの拠点を確保しておくといった、事業継続につながる計画を策定することが重要です。
事業継続力強化計画(BCP2.0)を策定しておくことで、火山災害による被害を受けた後でも、事業の早期再開を目指すことができます。
事業継続力強化計画(BCP2.0)などについては、こちらの記事をご覧ください。
地域社会との連携強化
企業は火山災害に備えて、地域全体で支え合う連携を強化しておきましょう。災害が起きた場合、地域内のほかの企業や組織との連携が不可欠です。災害用に備えた備蓄や機材などを、自社だけではなく地域全体でも使えるように準備します。その上で、備蓄共有や情報交換といった、相互支援を可能する企業同士のネットワークを確立することで、火山災害が起きた場合に、地域全体での復興を早めることにつながります。
火山災害が発生した場合は、物資の提供やボランティア活動を通じて、地域の再建に貢献し、企業の社会的責任を果たすことも重要です。
火山災害に備えて企業の防災戦略を万全にしよう
火山災害は、火山活動により発生するさまざまな現象が原因となり、人命や財産、さらには事業に対しても深刻な被害をもたらすことがあります。噴火は突然発生することが多いため、事前の備えが重要です。企業は活火山の分布確認やリスクアセスメント、事業継続力強化計画(BCP2.0)の策定などを通じて、従業員の安全と事業の安定を確保する必要があります。
火山災害への対応をあらためて確認し、企業としてできるかぎりの備えを行ってください。
<企業が行うべき安全配慮義務>
<自然災害と企業ができる備え>
地震災害とは?南海トラフ地震などに備えて企業ができる対策を解説
気象災害とは?台風や豪雨への備えなど企業ができる災害対策を解説
<事業継続力強化計画(BCP2.0)について>
MKT-2024-520
BCPのはじめの一歩 事業継続力強化計画認定をAIG損保がサポート >>
「ここから変える。」メールマガジン
経営にまつわる課題、先駆者の事例などを定期的に配信しております。
ぜひ、お気軽にご登録ください。
関連記事
パンフレットのご請求はこちら
保険商品についてのご相談はこちらから。
地域別に最寄りの担当をご紹介いたします。
- おすすめ記事
- 新着記事