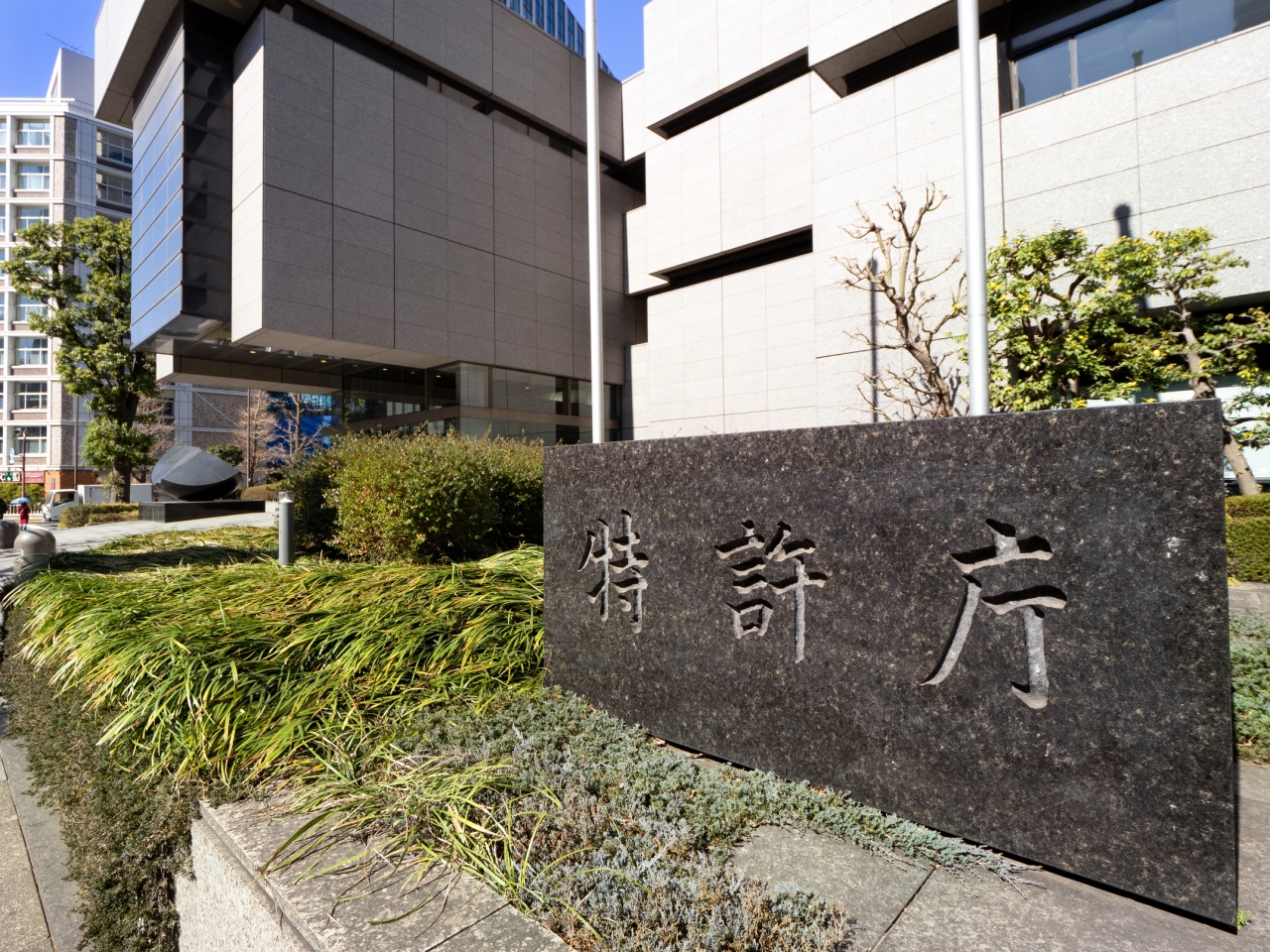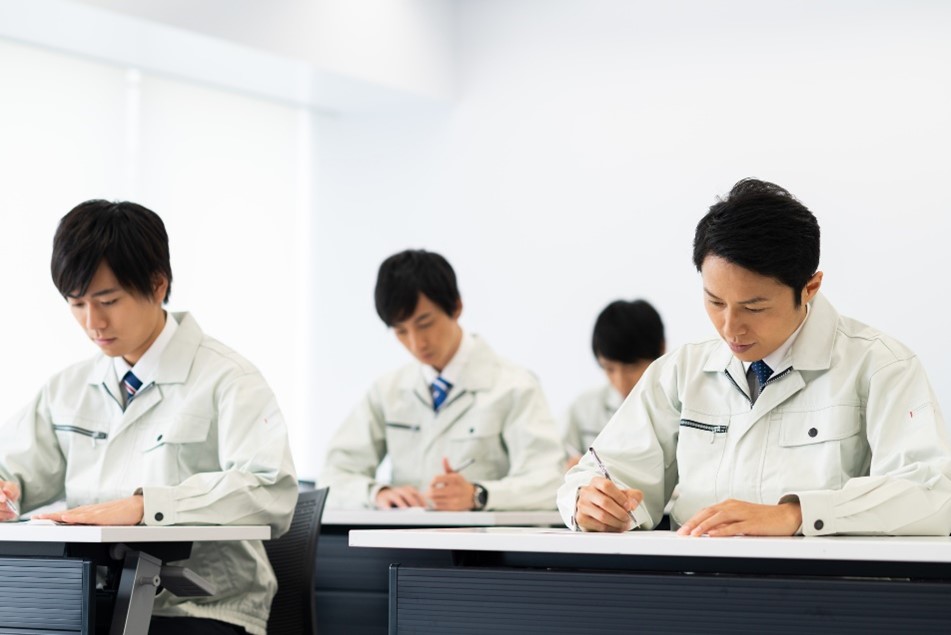-
土砂災害とは土砂が急激に移動して起きる災害のこと -
土砂災害の多い日本 -
土砂災害の種類と前兆現象 -
土砂災害に備えて企業ができる対策 -
命の安全と事業を守るため土砂災害への備えを実施しよう
土砂災害は大雨や地震などによって引き起こされ、大量の土砂によって周囲を埋め尽くす災害です。毎年のように日本各地に大小の被害をもたらし、建物を押し流したり、ときに人命を奪ったりすることもあります。短時間で広範囲に被害が及び、企業活動にも深刻な影響を与えることもある災害です。
ここでは、土砂災害の種類や、企業ができる備えについて解説します。
土砂災害とは土砂が急激に移動して起きる災害のこと
土砂災害とは、山や崖などの崩れた土砂が雨水や川の水と混じり、急激に移動することによって引き起こされる災害です。大雨、地震、火山活動など、さまざまな要因によって突発的に発生します。とくに集中豪雨や長期間の降雨は、大量の水分を含ませることで地盤を不安定にし、土砂災害のリスクを高めます。
土砂災害は、瞬時に広範囲にわたって甚大な被害をもたらすことがあるため、事前の備えと、事後の迅速な対応が必要です。
なお、土砂災害は人為的な土地改変など、人間の活動が直接的な原因となって引き起こされることがあります。この場合は自然災害ではなく、人為災害です。例えば、土木や建設工事などで山林を開墾するといった場合には、土砂災害を引き起こす可能性もあります。
土砂災害の多い日本
日本は、火山地や丘陵を含む山地の面積が国土の75%を占め、谷が多く、斜面は一般的に急斜面です。そのため、毎年のように土砂災害が起き、家屋の被害のほか、死者や行方不明者が出ています。
国土交通省の発表によると、過去41年間(1982~2022年)に起きた全国の土砂災害の平均発生回数は1,099件です。しかし、直近10年間(2013~2022年)の平均発生件数は1,446件と増えています。さらに、2023年に起きた土砂災害発生件数は、直近10年間の平均数を上回る1,471件でした。
このことから、日本における土砂災害の件数が徐々に増えていることがわかります。
■土砂災害発生件数の推移
画像引用:「令和5年は過去平均を上回る土砂災害が発生~令和5年の土砂災害発生件数を公表~」(国土交通省)
土砂災害が増加傾向にある日本では、2001年に制定された土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)によって、土砂災害のおそれがある地域を「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」に指定し、各自治体と連携して被害の想定される区域・時期の情報(土砂災害緊急情報)を提供しています。土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の違いは次のとおりです。
■土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の違い
土砂災害警戒区域 |
土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域 |
土砂災害特別警戒区域 |
避難に配慮を要する方々が利用する要配慮者利用施設等が新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、特定の開発行為を許可制とするなどの制限や建築物の構造規制等を行う区域 |
出典:「土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等について」(国土交通省)
土砂災害の種類と前兆現象
土砂災害は主に、土石流、地すべり、崖崩れ(急傾斜地の崩壊)の3つの種類に分類できます。3つとも、それぞれ特有の前兆現象があり、早期に察知することで、被害を軽減することが可能です。
ここでは、土砂災害の3つの種類と前兆現象について解説します。
土石流
土石流は、大雨などが原因で山の斜面が崩れ、その土砂と水が混じり合って、谷などの斜面を高速で流れ下る現象です。激しい雨が降った後の山地や、急勾配区間が長く土砂が多く堆積している谷で発生しやすく、非常に大きな破壊力を持ちます。
土石流の前兆現象には以下が挙げられます。
<土石流の主な前兆現象>
・川が急に濁る、流木が交じる
・雨が降っているのに川の水位が下がる
・山鳴りや地鳴りがする
・木が裂ける音や石がぶつかるような異常な音がする
地すべり
地すべりは、傾斜のゆるい斜面の土地が、地下水と重力の影響で下方へと滑り落ちる現象です。土石流や崖崩れと比べると速度はゆっくりで、地面が大きなかたまりのまま、何十年にもわたって少しずつ動いていることもあります。しかし、大雨や地震などがきっかけで突然滑り出す場合もあるため注意が必要です。
地すべりの前兆現象には以下が挙げられます。
<地すべりの主な前兆現象>
・地面や道路に亀裂や段差が発生する
・木が裂ける音がする
・井戸や池、沢の水が濁る
・崖から水が噴き出す
崖崩れ(急傾斜地の崩壊)
崖崩れは、勾配が急な斜面の土や岩が、突然崩れ落ちる現象です。崖崩れは、大雨によって崖に大量の水が含まれたり、地震の揺れによって発生したりします。瞬時に発生するため、崖下にある建物などに大きな被害をもたらす可能性があります。
崖崩れの前兆現象には以下が挙げられます。
<崖崩れの主な前兆現象>
・小石や土がパラパラと落ちてくる
・地鳴りがする
・崖などの斜面から水が湧き出る、またはそれまで湧いていた水が止まる
・崖にひび割れが入る
土砂災害に備えて企業ができる対策
ここでは、土砂災害に備えて企業ができることを解説します。
土砂災害は山や崖など、広範囲に対策が必要で、多くは国や自治体による大規模工事を必要とします。事業所が土砂災害のおそれのある地域に所在する場合、企業としては自治体への働きかけのほか、従業員の安全を確保することが大切です。
■土砂災害に備えて企業ができる主な対策
ハザードマップを活用
自社の事業所や施設が、土砂災害のリスクをどれだけ抱えているか、ハザードマップを活用して確認します。地理的な位置、過去の災害発生履歴、崩れやすい地形などを考慮に入れたリスクアセスメントを行い、自社の立地にどの程度の危険があるかを把握しておきましょう。また、土砂災害警戒区域がある自治体では、土砂災害のポータルサイトを作成し、過去の土砂災害や土砂災害のおそれのある区域の情報提供を行っています。
気象庁などが提供しているハザードマップなどは以下のとおりです。
<土砂災害などのハザードマップ>
「重ねるハザードマップ」(気象庁)
「土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)」(気象庁)
「地すべり地形分布図」(防災科研)
建物の構造強化と対策の実施
土砂災害特別警戒区域内に建物を建築するためには、土砂災害を防止するための対策工事が必要です。
土砂災害で想定される衝撃に耐えられるよう、建築物の構造規制があるため、すでに建物が立っている場合は、下記の図にあるような構造規制に則っているか確認しましょう。
■土砂災害に対する安全な構造規制の例
画像引用:「土砂災害警戒区域・特別警戒区域図について」(土砂災害ポータルひろしま)
従業員の安全対策
土砂災害が発生した際の、従業員の安全対策を実施します。具体的には、連絡方法の確立や、避難場所と経路の確認のほか、備蓄の用意などが挙げられます。
災害時に迅速かつ確実に従業員と連絡を取るための緊急連絡網を作成し、固定電話、スマートフォンなど複数の連絡手段を用意します。土砂災害のハザードマップにもとづいて、避難場所と避難経路についても周知し、作成した避難計画に沿って定期的に避難訓練を行うことも重要です。
なお、土砂災害警戒区域に事務所などがある場合、以下の警戒レベルを参考にして、必要であれば避難することを徹底しましょう。
■土砂災害警戒レベルと行動例
画像引用:「土砂災害警戒情報・土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)」(気象庁)
土砂災害によって道路が寸断され、事務所などが孤立する可能性も考慮し、非常食、水、救急キット、懐中電灯、乾電池、非常用電源、簡易トイレ、ブランケットなどの準備と保管も行います。
従業員の安否確認については、こちらの記事をご覧ください。
事業継続力強化計画(BCP2.0)の策定
土砂災害による事業への影響を最小限に抑えるため、事業継続力強化計画(BCP2.0)を策定します。
事業継続力強化計画(BCP2.0)は、自社の災害リスクに関する認識にもとづいて、企業の防災・減災対策を詳細に取り決める計画です。従来の事業継続計画(BCP1.0)とは異なり、計画の作成のみにとどまらず、実効性のある事業継続力の獲得と継続的な改善が重視されます。
事業継続力強化計画(BCP2.0)を策定しておくことで、土砂災害による被害を受けた後でも、事業の早期再開を目指すことができます。
事業継続力強化計画(BCP2.0)などについては、こちらの記事をご覧ください。
地域社会との連携強化
企業は土砂災害に備えて、地域全体で支え合う連携を強化しておきましょう。災害が起きた場合、地域内のほかの企業や組織との連携が不可欠です。災害用に備えた備蓄や機材などを、自社だけではなく地域全体でも使えるように準備します。その上で、備蓄共有や情報交換といった、相互支援を可能にする企業同士のネットワークを確立することで、土砂災害が起きた場合に、地域全体での復興を早めることにつながります。
また、土砂災害が発生した場合は、物資の提供やボランティア活動を通じて、地域の再建に貢献し、企業の社会的責任を果たすことも重要です。
命の安全と事業を守るため土砂災害への備えを実施しよう
土砂災害は、大雨や地震をきっかけに発生しやすく、命や財産に甚大な被害をもたらす可能性のある自然災害です。企業にとって土砂災害への備えは不可欠であり、ハザードマップの活用や、建物の構造強化などを検討し、従業員の安全を確保しましょう。また、災害発生後には迅速な情報収集とリスク管理による事業の早期再開が求められるため、事前の事業継続力強化計画(BCP2.0)の策定が重要です。
土砂災害への対応をあらためて確認し、企業としてできるかぎりの備えを行ってください。
<企業が行うべき安全配慮義務>
<自然災害と企業ができる備え>
地震災害とは?南海トラフ地震などに備えて企業ができる対策を解説
気象災害とは?台風や豪雨への備えなど企業ができる災害対策を解説
<事業継続力強化計画(BCP2.0)について>
MKT-2024-521
「ここから変える。」メールマガジン
経営にまつわる課題、先駆者の事例などを定期的に配信しております。
ぜひ、お気軽にご登録ください。
関連記事
パンフレットのご請求はこちら
保険商品についてのご相談はこちらから。
地域別に最寄りの担当をご紹介いたします。
- おすすめ記事
- 新着記事